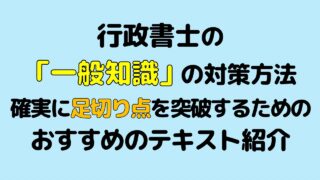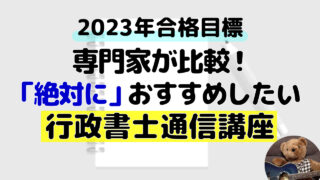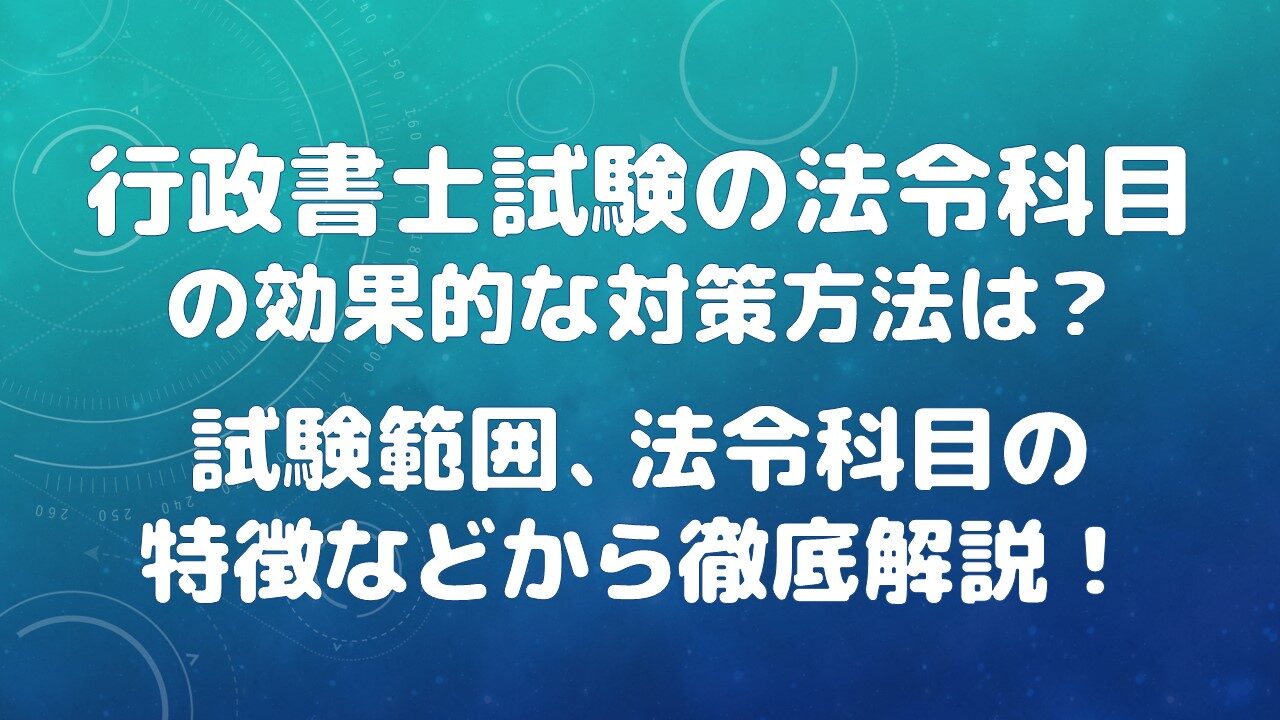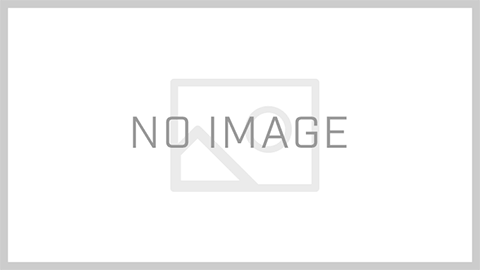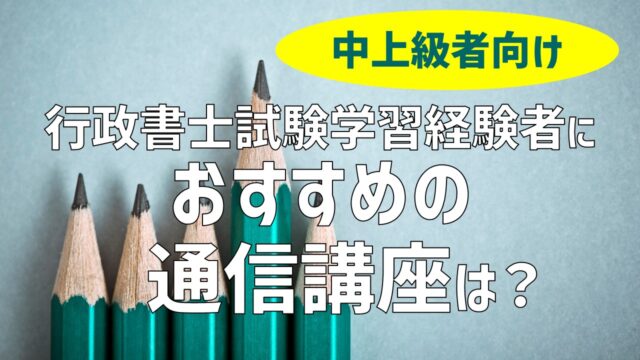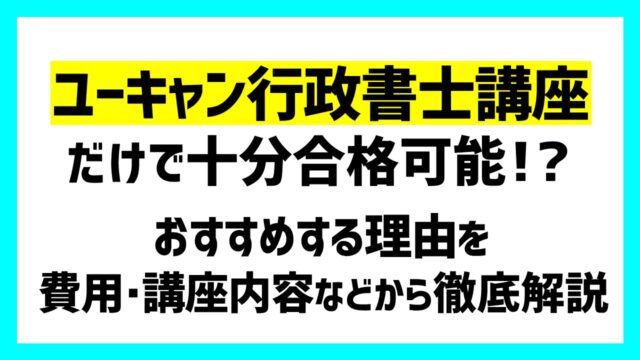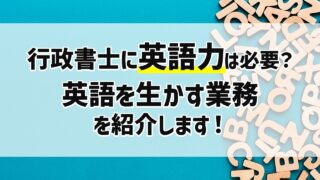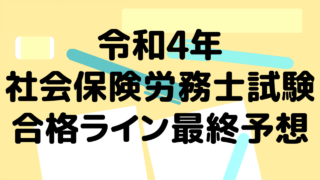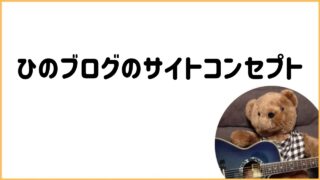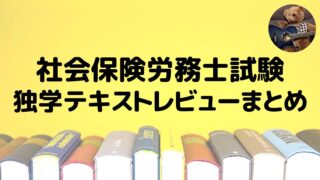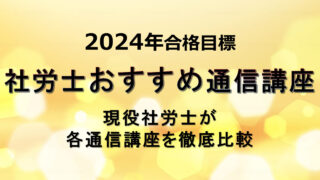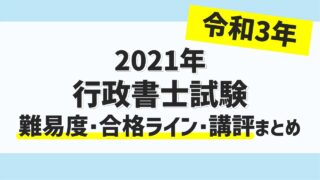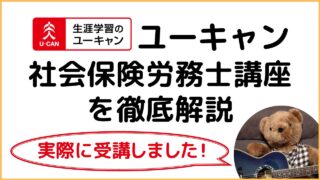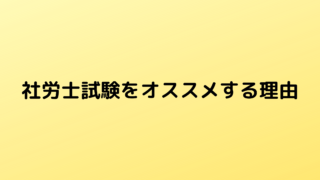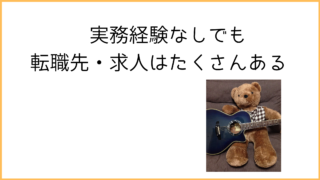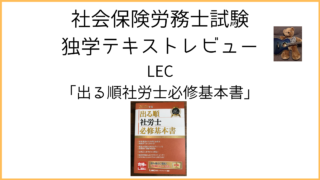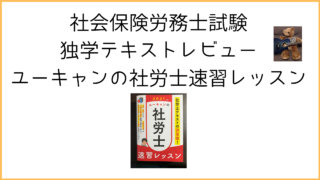行政書士試験の8割以上を占める法令科目の対策方法
行政書士を目指すみなさん、こんにちは!
行政書士試験は大きく2つに分かれるということを知っていましたか?
実は行政書士試験は、「法令科目」と「一般知識」に分けることができるのです。
「一般知識」では、政治や経済、文章理解など、文字通り一般的な知識が問われます。
一方、「法令科目」では大学の法学部で習うような法律のことが問われるのです。
行政書士と言えば、法律なので「法令科目」こそ行政書士試験の本質と言えます。
この記事では、行政書士試験のほとんどを占める「法令科目」について、その内容や対策方法をくわしく解説していきます!
・法令科目ってなに?
・具体的にどんな内容が出されるの?
・どの科目でどれくらい点数を取ればいいの?
そもそも行政書士試験についてあまり詳しくないという人でも簡単に理解できるよう、「とにかくわかりやすく」お届けしたいと思います。
ぜひ、最後までお付き合いください。
行政書士試験の法令科目とは?
ここでは、行政書士試験の「法令科目」について基本情報から解説します。
行政書士試験の法令科目とは
「法令科目」とは行政書士試験の8割以上を占める、法律関係のことについて問われる科目です。
行政書士の全体の配点は300点ですが、法令科目からは244点出題されます。
それに加えて、法令科目には足切り点が存在します。
244点中122点、つまり半分の点数が取れなければ、仮に一般知識で満点でも不合格となってしまうのです。
逆に一般知識についても足切り点があります。
まんべんなく得点することが求められるので行政書士試験が「難関国家資格」と言われるのも納得です。
もっとも、行政書士試験は全体の6割である180点を得点することが合格条件ですが、一般知識の難易度等も考慮すると、法令科目では140点から150点ほど得点する必要があります。
具体的な得点の取り方は後で解説します!
ここからは、法令科目を構成する5つの科目、
- 基礎法学
- 憲法
- 民法
- 行政法
- 商法・会社法
それぞれについて解説しながら傾向と対策を探っていきます。
基礎法学(配点8点)
基礎法学は、法律の基本的なことについて幅広く出題されます。
毎年2題出題され、配点は8点です。
配点が小さく、出題範囲が広くて対策もしにくいため、目標としては1問正解する程度で十分です。
憲法(配点28点)
憲法という存在がどんなものなのかについてはみなさんもご存じかと思います。
配点は28 点と試験全体の約1割を占め、出題傾向もはっきりしていることから、積極的に高得点を狙いたい科目です。
しかも、憲法はさまざまな法律を規定する国の最高法規なので、憲法を理解することはその他の法律を理解することに直結します。
積極的に勉強して高得点を目指しましょう。
民法(配点76点)
民法とは、一般市民同士の関係を規定する法律です。
配点が76点と非常に高く内容も複雑なので、最優先で勉強すべき科目です。
大学の法学部等でも最初に詳しく学習する分野なので、法律としての民法の重要度がうかがえます。
複雑で難解とはいえ、みなさんの身の回りや実生活と直結する部分が大きいので、勉強のしがいがある科目になっています。
民法を得意にして試験合格を近付けましょう。
行政法(配点112点)
行政法とは、その名の通り行政に関する法律から出題されます。
なんと配点が112点もあり、「行政法を制する者が行政書士試験を制する」と言っても過言ではない科目になっています。
特徴として、憲法の理解が行政法の理解につながりやすいという点があります。
最初は難解に思えるかもしれませんが、一度理解してしまえば得意科目になりやすい科目です。
しっかり勉強して合格に近づきましょう。
商法・会社法(配点20点)
民法が一般市民同士の関係を規律する法律なのに対して、商法・会社法は企業同士の関係や取引活動について規律する法律です。
基礎法学と同じく、配点が20点と低いのに学習量が多いので、「最悪ここは捨てる」という人もいるほどです。
とはいえ頻出分野はあるので、最低限そこは押さえておきたい科目です。半分くらい得点できれば御の字くらいで臨みましょう。
各科目の特徴がわかってもらえたかと思います!ここからは対策方法について解説します。
行政書士試験の法令科目全体に共通する勉強方法

5つの科目ごとの具体的な対策方法を解説する前に、法令科目全体に共通するポイントについて解説します。
科目ごとの勉強量、勉強する順番を考える
これは超重要です。
まず、先ほど説明した配点を思い出してください。
そうです。行政法と民法だけでなんと全体の6割以上を占めます。
勉強をするときは、ちゃんと配点に忠実に勉強量を配分することが大切です。
特に民法と行政法、また憲法には、十分な時間を割くようにしてください。
また、勉強する順番も非常に大切になってきます。
憲法ついて説明したところで言ったように、憲法はその他の法律を規律する国の最高法規です。
つまり、憲法の理解が他の法律の理解につながります。
また、民法は非常に複雑で、考えなければならない事例や条文がとても厳密で複雑になっています。
憲法と民法は、順番的にも優先して勉強するようにしましょう。
細かいことかもしれませんが、こう言ったことの積み重ねが合格を引き寄せます!
法令科目の配点が全体の約81%を占める
法令科目の配点は試験全体の約81%です。
対策しやすいからといって、一般知識の文章理解や個人情報保護等の科目に逃げることはやめましょう。
法令科目を避けていては、一生行政書士試験に合格することは出来ません!!
記述式の問題が重要
記述式がある科目は、「行政法」と「民法」です。
この2科目の重要度が表れていますね。
また、記述式には60点もの配点がなされています。
しかし、記述式は解答の自由度の高さゆえに得点が取りにくい部分です。
意識してほしいこととしては、「部分点を稼ぐこと」です。
完璧な答案を書くことは難しいですが、これを意識するだけで得点を底上げできます。
部分点が取れるということは、問題にまつわるキーワードが抽出できれば得点に近づけますね。
行政書士法令科目の具体的な対策方法
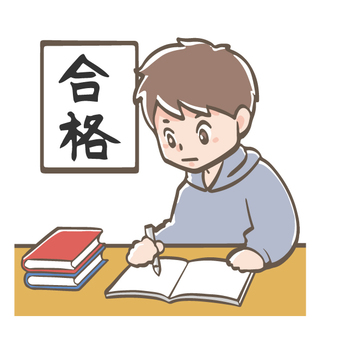
ここでは、みなさんが気になっている科目ごとに具体的な対策方法について解説していきます。
基礎法学
基礎法学を勉強するときは、「演習を中心」に勉強しましょう。
また、法令科目なかでも「最後に勉強」することも大切です。
基礎法学は法律全体を問う問題なので、他の法律の勉強を通して全体像を把握してから勉強した方が効率的です。
過去問を中心に演習し、論点や重要度の高い部分を把握してください。
憲法
憲法の学習で重要になることは、「判例と条文を大切にすること」です。
ひっかけ問題が多いのが出題の特徴なので、この2つを大切にして‘’厳密に‘’理解を深めることが必須です。
テキストや講義で学習する際も、六法や判例集を参照してみっちり学習してください。
それができればあとは過去問で演習を積むのみです。
民法
民法の学習は非常に難しいです。
おそらく、一度講義を聞いたりテキストを読んだりするだけでは理解できません。
そこで重要なのは、「わからなくても先に進むこと」です。
早く進んで何度も繰り返し学習することで、民法全体を貫くものが見えてきます。
問題を解く際は、個人と個人の法律関係を図に書いたりして整理すると効果的です。
繰り返し学習しながら、最後は過去問を中心にして知識を確固たるものにしましょう。
行政法
行政法は1番配点の高い科目です。
ですが特に難解ということはないので、大切なのは「過去問演習」になります。
というのも、出題数が圧倒的に多いからです。
配点が高いということは出題数も多いということになります。
その分、過去問には行政法に関する情報がたくさん詰まっています。
過去問を繰り返し解いて、なるべく多くの出題をクリアにしていきましょう。
商法・会社法
この科目は本当に学習効率が悪いです。
範囲が広いので、実は過去問演習が有効とも言い難いんです。
ですが、頻出分野はあります。
それは「株式」と「会社の機関」です。
この2つを重点的に勉強して、あとは知っている問題が出ることを祈る、こんなスタンスでかまいません。
行政法、民法、憲法がしっかり得点出来ていれば、ここで得点出来なくても合格することが出来るのが行政書士試験です。
行政書士試験法令科目の効果的な対策方法まとめ
法令科目の対策方法について解説しました。 まとめると、
・法令科目は試験全体でみると配点が高い
・民法と行政法を中心に勉強する
・基礎法学と商法・会社法は勉強効率が悪い
・憲法の理解が全体の理解につながる
こう言ったことがわかってもらえたかと思います。
この記事がみなさんの法令科目対策の手助けになれたのなら、これほど嬉しいことはありません。
みなさんの合格を、心から祈っています。