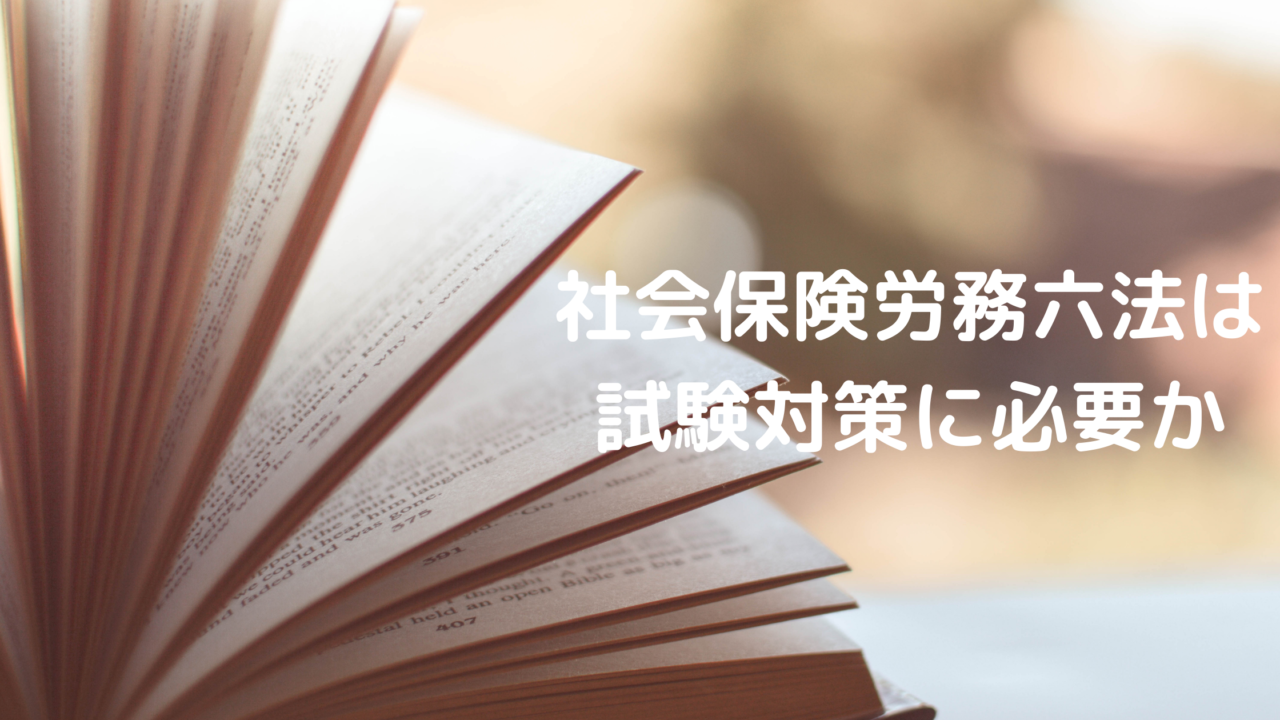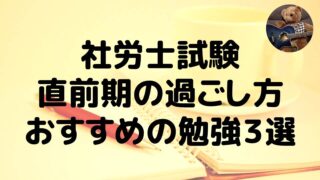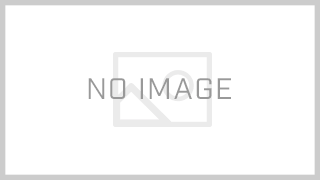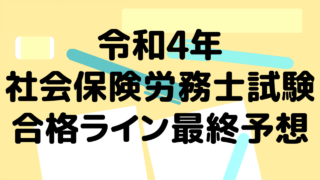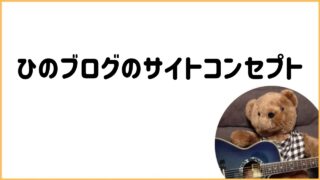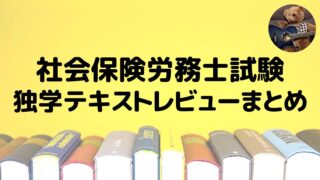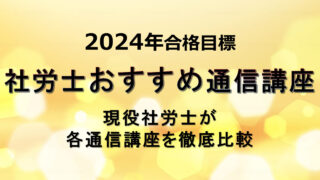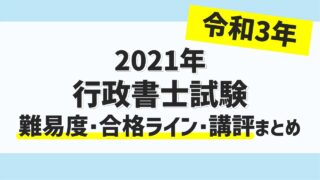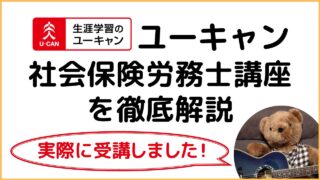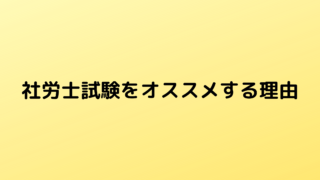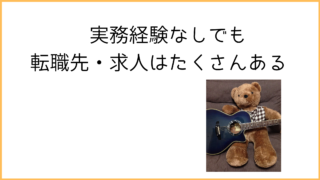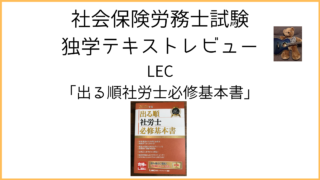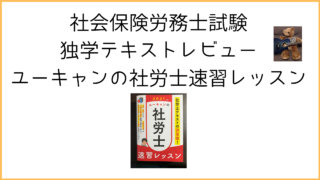- 社労士試験対策に社会保険労務六法は必要なの?
- 法律の読み方は勉強しておいた方が良いのかな?
この記事ではこのような疑問にお答えすべく、記載を進めていきたいと思います。
それでは早速結論です。
結論:社会保険労務六法は社労士試験対策には不要
社会保険労務六法は社労士試験対策としては不要です。
そもそも社会保険労務六法とは
全国社会保険労務士連合会が発行している、社労士の業務範囲に特化した、社会保険・労働関係の各法令をまとめた本です。
試験勉強をしている人は、テキストだけでなくてこういった法令集も確認しなければいけないの?
と疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、試験対策には不要で、テキストに集中していただければと思います。
ちなみに私は平成29年版を試験勉強用に買ってしまいました。
試験対策としては入りませんでしたが、机の上に置いておいて、たまに法令をざっと見渡すだけで「将来はこれを使いこなせるようになりたい!」とモチベーションアップにはなりました。
六方は社労士試験対策には不要だが、必要ば場面は?
社労士試験対策には全く不要である六法ですが、合格後は使用する機会があります。
社労士六方が必要な場面① 事務指定講習
事務指定講習を受講される方は早速六法の出番です。
教材として組み込まれていますので、事務指定講習の課題提出などにあたって活用することとなります。
社労士試験の勉強で法律の勉強を散々してきたと言っても六法を使いこなすことはなかなか難しいと思われますが、法律を読み解く力は今後も必要ですので、事務指定講習の機会を通じて学びたいですね。
社労士六方が必要な場面② 開業後・勤務登録後
開業や勤務登録をした後には六法の出番はあるのでしょうか。
私は、必要ないと思います。
法令を読み解く力は必要ですが、六法自体は必要ありません(使うことを否定するものではありません)
なぜなら、ネット上に最新法令があるからです。
これは国が掲載しているサイトで、多少のタイムラグはありますが基本的には最新法令となっています。
また、ネットですので文章検索も可能です。
六法が置いてあるだけで、「この人凄そう」という権威性は利用できるかもしれません。
社労士六法はいらないけど、試験で法律を読み解く力は必要
社労士は法律の専門家ですので、六法がネットで代用できるとしても法律を読み解く力は絶対に必要です。
そのためにも六法を手元に置いておいて、法律そのものの書き方になれておくということは良いかもしれません。
例えば、実務で必要となった知識の部分をいちいち六法に戻って法律を確認してみるなど。
手間ですが、自分がやっている仕事がハッキリと法律に基づいてやっているんだと思えるとなんだか楽しいです
法律を読む基礎知識がまだ不安だと思う方はこの本がオススメです。
この本、私が行政書士の試験を受けようと思った時に購入した本ですが、
例えば法律の「又は」と「並びに」の違いや「及び」と「若しくは」など、わかっているようでわからない法律の知識を、法制局という法律を細かく審査するエリートが書いた本です。
エリートが書いたと言えど、内容は入門書となっているので読みやすく、法律の条文への抵抗意識を和らげてくれます。
社労士試験対策に社会保険労務六法は必要か まとめ
この記事では社会保険労務六法は試験対策に必要かということで書かせていただきました。
試験対策には不要で、今後もあまり必要ないです。
ですが、法律を読む力は絶対に必要なので、社労士試験合格後の時間がある時に、法律に慣れるためにも、また多少の権威性を持たせるためにも六法があってもいいのではないでしょうか。